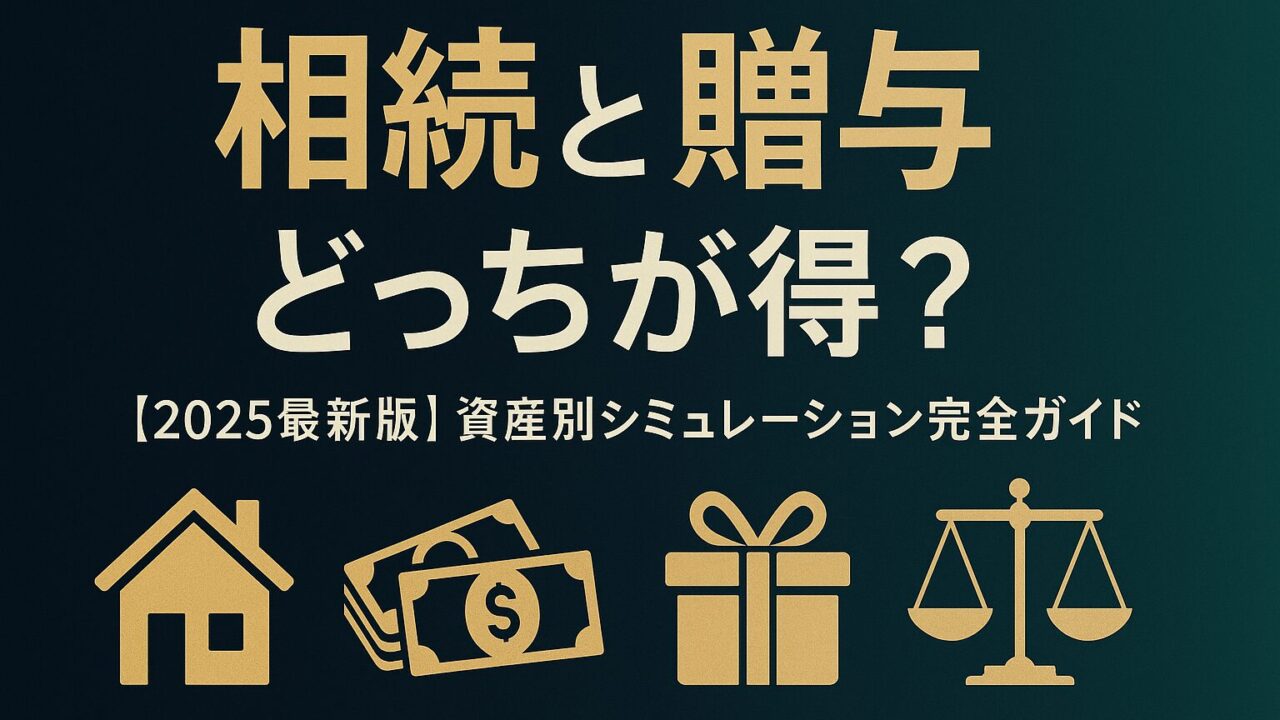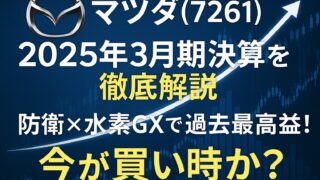Contents
この記事の要点・結論
この記事では、「相続と贈与どちらが得なのか」を徹底比較し、最適な資産承継プランを検討するポイントを詳しく解説します。 まず結論として、3,000万~5,000万円程度の資産であれば相続のほうが税コストを抑えやすく、一方で1億円超の資産をお持ちで、かつ相続人が少ない場合には計画的に贈与や特例を組み合わせることが節税のカギになります。 また、2024年から始まる生前贈与加算期間の段階的延長にも注意が必要です。従来3年だった加算期間は最長7年へ移行するため、「2025年以降は一律3年に短縮される」わけではありません。 つまり、贈与をいつ行うかによって相続時に合算される年数が異なり、結果的に税額が変わります。二次相続リスクや家族構成も踏まえながら、どこまで贈与で減らせるかを試算しておくことが重要です。まず押さえる!相続税 vs 贈与税 基本の仕組み
2025 改正:生前贈与加算「3 年」へ短縮? 実際は段階的に延長
- 2024年1月より適用された贈与加算ルールは、従来3年から最大7年へ延長が決定済み(2023年財務省)
- 2026年12月31日までの相続は3年加算、2027~2030年の相続は「2024年1月1日以後の贈与」を全て加算し、2031年以降は7年加算
- 一部で「2025年改正で3年に短縮する」という話があるが、現時点で短縮の法案はなく、むしろ延長が本筋
税率&控除を表で比較【2025最新版】
| 相続税 | 贈与税(暦年課税) | 贈与税(相続時精算課税) | |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×相続人の数 | 110万円/年 | 2,500万円(特別控除)+110万円(2024年導入) |
| 最高税率 | 55% | 55%(一般贈与)/45%(特例贈与) | 一律20% (最終的に相続で精算) |
| 課税方法 | 超過累進課税 | 超過累進課税 | 特別控除後は20% |
| 非課税枠 | 生命保険500万円× 法定相続人など | なし (基礎控除110万円のみ) | 110万円/年 (申告不要・持ち戻し不要) |
| 加算制度 | 生前贈与加算: 3~7年間段階的に延長 | 毎年110万円まで非課税 (暦年課税) | 相続時に合算精算 (超過分は相続税と合算) |
ケーススタディ① 資産3,000万円・子2人
贈与なし vs 10年分割贈与で比較
- 家族構成:子ども2人、親(被相続人)が保持する資産総額3,000万円
- 現預金のみで大きな不動産や株式はなし
- 配偶者の有無によって多少変動するが、ここでは配偶者がいない前提
ケーススタディ② 資産1億円・自宅あり
小規模宅地特例+暦年贈与の組み合わせ
- 自宅の敷地評価額が約6,000万円(都市近郊で200平米程度)
- 預貯金・有価証券で4,000万円
- 家族構成:配偶者1人+子2人
ケーススタディ③ 資産3億円・株式中心
相続時精算課税+非上場株納税猶予の活用
- 非上場株式(親族企業の株など)2億円分
- 不動産(アパートや土地)5,000万円相当
- 預貯金や証券など5,000万円
- 相続人が子1人または2人程度の想定
贈与で得する人・相続で得する人 5つの判断軸
1 資産規模 2 家族構成 3 収益不動産の有無 4 将来の医療・介護費 5 税率ギャップ
- 1 資産規模…5,000万円以下なら相続税がかからない可能性が高く、贈与の費用対効果は低い。一方1億円超では贈与と特例の組み合わせで大幅節税の余地
- 2 家族構成…相続人が多いほど基礎控除や生命保険非課税枠が有利。相続人が少ないなら生前に贈与で分散を図るのも手
- 3 収益不動産…賃貸物件があると相続評価が下がりやすい反面、贈与時の評価は時価に近い可能性あり。借入金状況も考慮必須
- 4 将来の医療・介護費…親が高齢化するほど、贈与しすぎると資金不足の懸念。家族信託を活用し、必要な資金を確保しながら贈与プランを実施可能
- 5 税率ギャップ…相続も贈与も最高55%だが、毎年110万円ずつ小口贈与すれば負担なく資産移転できる利点が大きい
節税テクニック6選
1 暦年贈与110万円活用 2 教育資金一括贈与 3 生命保険非課税枠 4 家族信託 5 不動産建替え 6 二次相続対策
- 1 暦年贈与110万円…最もベーシックな生前贈与。一度に大きく移せないが、コツコツ長期間続けると効果大
- 2 教育資金一括贈与…祖父母から孫への1,500万円非課税など。2025年以降も期限延長が検討され、活用価値は高い
- 3 生命保険非課税枠…500万円×法定相続人の分が非課税。資産規模が大きいほど、この枠を最大限活用すると節税効果が高い
- 4 家族信託…直接の節税制度ではないが、委託者の認知症リスクに備え、暦年贈与や財産管理を柔軟に続けられるメリット
- 5 不動産建替え…現金をアパートやマンションへ建替えると、相続評価が下がりやすい(借家建付地評価減)。借入金を利用し評価減を狙う手法も多い
- 6 二次相続対策…配偶者に全てを相続させると、一時的には税負担をゼロにできるかもしれないが、配偶者亡き後の二次相続で1.4倍の税になる事例が多い
※相続の手続き・節税対策にあたっては以下の記事も参考にしてください
- 相続トラブル事例10選と弁護士直伝の解決策 — 典型的な“争族”パターンを事例別に分析し、弁護士視点で予防・解決アプローチを解説。
- 相続と贈与どっちが得?資産別シミュレーション&最適節税プラン — 税率・控除を表で比較し、ケーススタディで最適な節税ルートを提案。
- 相続手続きチェックリスト15項目|期限と必要書類を完全ガイド — 死亡直後から10か月までの必須タスクを時系列で整理し、書類と届出先を漏れなく網羅。
まとめ
「相続と贈与のどちらが得か」は、単純な税率だけでは決められません。資産額や家族構成、収益不動産の有無、さらには二次相続リスクまで考慮した上で、総合的に試算することが大切です。 たとえば3,000万円程度の資産ならほぼ相続税ゼロにでき、贈与の手間や費用をかける必要性が小さいでしょう。 一方、1億円以上の資産を保有する場合、贈与と特例を組み合わせれば相続税を2割~3割以上抑えられる余地があります。 さらに2026年末までは生前贈与の加算期間は3年のままですが、2027~2030年の相続では「2024年1月1日以後の贈与分」を全て加算し、2031年以降は7年加算となります。 贈与するタイミングや金額を間違えると、思わぬ形で相続税が増える可能性があるため、早めの対策が肝心です。 また、二次相続の税負担増加問題は多くの家庭で起こり得ます。配偶者が全額相続すると一次相続はゼロでも、二次相続で大きく課税される典型例が後を絶ちません。 家族信託や生命保険、不動産評価減なども含め、多角的にプランを設計することが必要です。 最終的には家族全体の資金ニーズや将来像に合わせた長期シミュレーションが不可欠であり、専門家(税理士や信託銀行等)への相談を強くおすすめします。 最適な形で「贈与か相続か」をデザインし、余計な税金を払うことなく円満な資産承継を実現していきましょう。よくある質問
- 生前贈与加算期間は結局何年ですか? 2024年以降は段階的に3年→最長7年へ延長され、2031年相続開始分から7年加算になります(詳細は国税庁)。
- 110万円の暦年贈与はもう意味がないのですか? 加算対象には含まれますが、長期分散すれば平均税率を下げられるため依然有効です。
- 相続時精算課税と暦年課税は併用できますか? 同一贈与者からはどちらか一方の選択制ですが、贈与者ごとに方式を変えることは可能です。
- 小規模宅地等の特例は賃貸アパートでも使えますか? 貸付事業用宅地として200㎡まで50%評価減が適用できます。
- 生命保険の非課税枠はいくらまでですか? 「500万円×法定相続人」の死亡保険金は相続税がかかりません。
- 配偶者への贈与は加算対象になりますか? 婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産等2,000万円までの贈与は加算対象外です。
- 二次相続を見据えた分割方法は? 一次相続で配偶者控除を使い過ぎず、子へ均等分割することで総税負担を抑えられます。
- 専門家へ相談するタイミングは? 資産5,000万円超なら、税理士や信託銀行に早めにシミュレーションを依頼しましょう。
参考サイト
- 国税庁|相続税の概要と課税価格の計算― 基礎控除や累進税率の公式解説で制度の全体像を確認できます。
- 国税庁|贈与税のしくみ(暦年課税・特例税率)― 暦年贈与と特例贈与の税率表を掲載しており試算の根拠に便利です。
- 財務省|令和7年度(2025年)税制改正大綱 概要― 生前贈与加算の段階的延長など最新改正ポイントを公式に確認できます。
- 野村證券|相続と贈与のどちらが得か?資産別シミュレーション― 金融機関の試算例でケーススタディの具体的数字が参考になります。
- 三井住友信託銀行|小規模宅地等の特例で節税するポイント― 宅地評価減の詳細と適用要件が図解で分かりやすい記事です。
- りそな銀行|生命保険を活用した相続税対策― 死亡保険金の非課税枠や契約形態の注意点を具体例付きで解説しています。
初心者のための用語集
- 生前贈与加算― 相続開始前一定期間(現在は最長7年)に行った贈与を相続財産に足し戻して課税する仕組み。
- 暦年贈与― 毎年1月1日〜12月31日の贈与額から基礎控除110万円を差し引いて課税する一般的な贈与税方式。
- 相続時精算課税― 2,500万円+毎年110万円まで非課税、超過分は一律20%で課税し、贈与者死亡時に相続税で精算する制度。
- 基礎控除― 相続税計算時に「3,000万円+600万円×法定相続人」で無条件に差し引ける非課税枠。
- 小規模宅地等の特例― 居住・事業用の宅地評価額を最大80%減額できる相続税の節税特例。
- 生命保険非課税枠― 死亡保険金にかかる相続税を「500万円×法定相続人」の範囲で非課税とする優遇措置。
- 二次相続― 配偶者が一次相続で遺産を取得した後、その配偶者が亡くなった際に発生する二度目の相続。
- 非上場株納税猶予― 事業承継時に一定条件下で自社株にかかる贈与税・相続税の納税を猶予(または免除)する制度。
- 特例税率― 親や祖父母から18歳以上の子・孫へ贈与する際に適用される、一般税率より緩やかな贈与税率。
- 加算期間― 生前贈与加算の対象となる年数。2024〜2030年は段階的に延び、2031年相続開始分から7年固定。
相続に関する参考記事
遺言書の作成から相続税対策まで、トラブルを回避しつつ損をしないための実践ノウハウを厳選しました。気になるテーマをチェックして、安心・円満な相続にお役立てください。
- 相続争いを防ぐ遺言書テンプレート — 自筆・公正証書の書き方と注意点を具体例付きで解説。テンプレート活用で無効リスクを最小化。
- 相続の基本|初心者ガイド — 法定相続人・遺産分割の流れをわかりやすく整理。まず押さえるべき手続きと期限を総まとめ。
- 相続税はいくら?2025年シミュレーションと節税策 — 税額早見表とシミュレーションで負担額を試算。小規模宅地等特例などの節税テクニックも紹介。
編集後記
先日、税理士として30年以上のキャリアを持つ友人から紹介されたのが、千葉県在住の会社役員Aさん(68歳)でした。Aさんは退職金として1億2,000万円、上場株式8,000万円、自宅(土地評価9,000万円・建物1,500万円)を保有し、配偶者と子ども2人の4人家族。2024年の生前贈与加算延長を知り「暦年贈与で毎年500万円ずつ移せば十分」と思っていたものの、筆者が試算すると10年後の相続時に課税価格が基礎控除を大きく上回り、相続税総額2,400万円に達する結果が出ました。 そこで提案したのが①小規模宅地等の特例と②相続時精算課税の組み合わせ。自宅は330㎡内だったため評価額を80%減の1,800万円へ圧縮し、株式は相続時精算課税で2,500万円+110万円控除を利用し一律20%課税に切替。さらに死亡保険1,500万円(被保険者Aさん、受取人子2人)を活用し500万円×相続人3人=1,500万円を非課税で確保しました。結果、一次相続想定税額は2,400万円→890万円に大幅減。配偶者が80歳時点で生活費を確保できるよう、現金2,000万円を残すライフプランも同時に作成しています。 Aさんは「数字で⾒ると節税と生活資金の両立がはっきりわかる」と納得し、今年3月に信託銀行と家族信託契約を締結。認知症リスクに備え、毎年110万円の暦年贈与を子ども名義の教育資金として継続する計画です。今回のケースは、加算期間の延長と二次相続を見据えた宅地評価減を組み合わせることで実現できた好例といえるでしょう。読者の皆さまも、ぜひ早い段階から専門家とシミュレーションを行い、ご家族に最適な承継プランを検討してみてください。免責事項
こちらの記事は相続に関する一般的な知識提供を目的としています。記事内容は執筆時点での情報に基づいておりますが、法律や規制は変更される可能性があるため、最新かつ正確な情報については関連機関や専門家にご確認ください。 当サイトに掲載されている専門家選定方法や見積もり比較のポイントは、あくまで参考情報であり、特定の相続専門家を推薦・保証するものではありません。実際の契約や専門家選定においては、ご自身の責任において十分な調査と検討を行ってください。 また、本記事で紹介している事例やトラブル回避策を実践されても、すべての問題が解決されることを保証するものではありません。個々の状況や条件によって適切な対応は異なる場合があることをご理解ください。 当サイトの情報に基づいて行われた判断や行動によって生じたいかなる損害についても、当サイト管理者は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。相続に関する無料相談、随時受付中!
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。当ブログでは、相続に関するあらゆるお悩みにお応えします。 初めての相続手続きをお考えの方から複雑な案件をお持ちの方まで幅広く対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。無料で相続手続きの流れや費用の目安、専門家選びのポイントなどをアドバイ スさせていただきます。あなたの相続手続きを全力でサポートいたしますので、一緒に安心できる相続手続きを進めていきましょう!ABOUT ME